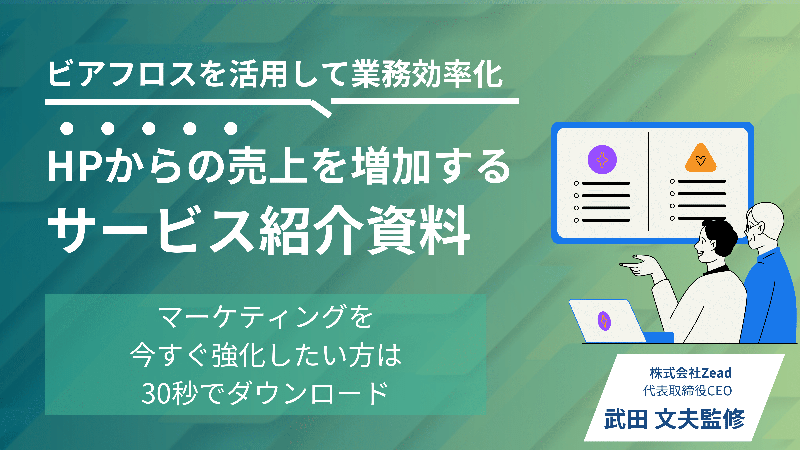目次
マルチタッチアトリビューションとは

マルチタッチアトリビューションとは、商品やサービスを購入するまでに顧客が通過したすべてのタッチポイント(広告、SNS、メルマガ、ウェブサイトなど)を解析し、最終的なコンバージョンに対して各施策がどの程度貢献したかを測定する手法です。
従来のラストクリックやファーストクリックなど単一指標とは異なり、複数の接点を評価して総合的な効果を把握できるのが特徴です。購買行動のプロセスが複雑化し、顧客は検索エンジン、SNS、広告など多様なメディアを経由するケースが増えています。
そのため、どの接点が最も効果的かを把握することは、マーケティング予算の最適化や施策の改善につながります。マルチタッチアトリビューションの導入によって、企業はデータドリブンな意思決定を行いやすくなり、市場競争において有利な立場を築ける可能性が高まります。
シングルタッチモデルとの違い
シングルタッチモデルとは、例えばラストクリック(最後にクリックされた広告に100%の成果を割り当てる)やファーストクリック(最初に接触した広告に100%割り当てる)など、コンバージョンに直接関与した1つの接点のみを評価する手法です。シンプルで導入しやすい反面、途中で重要な関係を果たした他の接点を見落としてしまう問題があります。
これに対し、マルチタッチアトリビューションでは複数のタッチポイントに加点し、購買行動全体を多角的に評価するため、より精度の高い分析が可能です。施策間の相乗効果を把握できることが大きな利点といえます。
マルチタッチアトリビューションがもたらすメリット
マルチタッチアトリビューションを導入すると、企業のマーケティング戦略に多面的なメリットがあります。ここでは代表的なメリットを三つ挙げ、その重要性を解説します。
マーケティング予算の最適化
複数の接点を包括的に評価することで、各施策の真の貢献度を把握できます。例えば、Aという広告とBというSNS投稿が組み合わさることで初めて効果を発揮しているケースがある場合、ラストクリックモデルだけでは見逃される可能性があります。
マルチタッチアトリビューションなら、それぞれの施策に適正な評価を割り振ることができ、予算をより効果的に投じられます。
同時に、効果の薄いチャネルやキャンペーンを早めに把握し、テコ入れや停止の決断がしやすくなるのもメリットです。結果として投資対効果(ROI)の向上や、マーケティング全体の効率化が期待できるでしょう。
顧客行動の詳細な把握
顧客が購買に至るまでのステップは多様な経路を辿る場合が多いです。マルチタッチアトリビューションを活用すれば、最初の接点から最終的なコンバージョンまでの全行程を可視化できるため、顧客がどのタイミングで何を求めているかを深く理解できます。
これによって、見込み客が最も興味を持ちやすい接点や、離脱しやすいポイントなどが明確になります。顧客インサイトを得られるため、商品開発やカスタマーサポートなど、マーケティング以外の領域でも改善のヒントを得ることが可能です。
施策の組み合わせ効果の検証
マーケティング施策は、単独で動いているわけではありません。ある広告と別のSNS投稿が組み合わさることで、相乗効果を生み出すケースがあります。マルチタッチアトリビューションでは各タッチポイントの役割をバランスよく数値化できるため、どの施策の組み合わせが最も大きな効果を発揮するかを把握しやすくなります。
例えば、新規顧客獲得には検索広告とメルマガが相性良いのか、それともリマーケティング広告とSNSキャンペーンが相性良いのかといった点を定量的に検証できます。このような知見が得られれば、今後のプロモーションを大幅に効率化できるでしょう。
マルチタッチアトリビューションの主要モデル
マルチタッチアトリビューションにはさまざまなモデルが存在します。企業のビジネス特性や顧客行動、扱うデータの種類によって最適なモデルは異なります。ここでは代表的なモデルをいくつか取り上げ、その特徴を簡潔に説明します。
線形モデル(リニアモデル)
線形モデルは、購買に至るプロセス上のすべての接点に対して、均等に貢献度を割り当てる方法です。最初の接点から最後の接点まで、例えば合計が100%になるように均等に分配します。シンプルでわかりやすい反面、特定のステップが大きく影響を与えたとしても、同じ比率しか割り当てられないため、精度の問題が発生することがあります。
U字型モデル
U字型モデルでは、最初の接点と最後の接点に重点を置き、その2つに高めの貢献度を割り振り、それ以外の接点は均等に残りの比率を分配します。最初に出会ったチャネルと最終的に購入を決意したチャネルを重要視する考え方です。ある程度バランスが取りやすい一方で、中間ステップの影響をどこまで正確に評価できるかが課題となります。
W字型モデル
W字型モデルは、最初・中間・最後といった重要な接点に大きなウェイトを割り振り、残りを他のステップに分配する方法です。B2Bのセールスプロセスなど、顧客が特定のフェーズで大きくステップアップする商材に向いているとされています。ただし、どのステップを「重要な接点」と設定するかについては、企業ごとの分析が必要になります。
タイムディケイモデル
タイムディケイモデルでは、コンバージョンに近いほど重みを大きくする手法を用います。購買の意思決定に近い時期での施策をより評価したいときに有効です。最新情報が購買行動に大きく影響すると想定される場合に選択するケースが多いですが、初期段階でのブランディングの効果を過小評価するリスクがあります。
マルチタッチアトリビューションの導入ステップ

マルチタッチアトリビューションを実際に導入するには、単にツールを導入するだけでは不十分です。データの収集や組織体制の整備など、段階的なアプローチが求められます。ここでは代表的な導入ステップを三つ挙げて解説します。
データの統合と整理
まずは、複数のチャネルから発生する顧客データを一元的に管理する基盤を構築します。ウェブ解析ツールや広告プラットフォーム、SNS、CRMなど、さまざまなデータソースを連携させ、顧客行動をタイムラインで追えるようにします。
この際、データフォーマットの違いや重複情報、プライバシー規制への対応など多くの課題が出てくるため、データクレンジングや標準化のプロセスが重要になります。精度の高い分析を行うためには、まず正確で一貫性のあるデータが必須です。
モデルの選定と検証
データ基盤が整ったら、どのモデルを採用するかを検討します。企業の業種や商材の特性、顧客行動のパターンなどを考慮し、線形やU字型、あるいはカスタムモデルの使用を決めます。
導入前に小規模のデータでテストを行い、精度や再現性を評価してから全社導入に移行するとリスクを抑えやすいです。モデルの妥当性を検証することで、どのポイントにどれだけ重みを置くべきかが明確になり、施策の改善がスムーズに進みます。
運用と継続的な改善
モデルを本番環境で運用し始めたら、定期的に結果をモニタリングし、施策への反映を行います。例えば、特定の広告が過大評価されている可能性があるなら、別のモデルを試したり、重み付けを変更したりといった微調整を続けることが重要です。
また、顧客行動や市場環境は常に変化します。新しい広告チャネルが登場したり、ユーザーの趣味嗜好が変わったりするため、継続的にモデルの更新や再学習が求められます。こうしたアジャイル的な運用を行えば、マルチタッチアトリビューションの恩恵を最大限に享受できます。
マルチタッチアトリビューション導入の注意点
マルチタッチアトリビューションには多くのメリットがある一方、誤った運用や過度の期待はリスクを伴います。特に注意が必要なポイントを三つ取り上げて解説します。
過度なデータ依存とノイズ
膨大なデータを解析することで高い精度の結果が得られる反面、データに含まれるノイズや誤差も増えがちです。機械学習やモデルに依存しすぎると、重要なビジネスロジックや経験則が軽視される可能性があります。
分析結果を活かすには、担当者が背景や文脈を把握し、データだけでは見えにくい要素を総合的に判断する姿勢が重要です。データ主導と人の知見をうまく組み合わせることが成功へのカギといえます。
プライバシーと法規制の考慮
複数のデータソースを統合する場合、顧客の個人情報や行動履歴を扱う可能性が高まります。個人情報保護法やGDPRなどの法規制を順守し、適切に匿名化や権限管理を行うことが不可欠です。
プライバシーへの配慮を怠ると、企業の信用が損なわれ、ブランドイメージに悪影響を与えるだけでなく、法的リスクを負うことにもなりかねません。導入前に法務部門や専門家のアドバイスを得ると安心です。
組織的な連携と文化の醸成
マルチタッチアトリビューションを導入しても、サイロ化した組織ではデータを共有できず、成果が十分に発揮されない恐れがあります。マーケティング部門だけでなく、営業や経営陣と連携し、分析結果を意思決定に反映させるための組織文化が重要です。
また、社内でのデータ活用リテラシーを向上させる研修や、共通KPIの設定など、全社的な取り組みも視野に入れるべきです。分析ツールやモデルを導入するだけではなく、それらを活かすための体制づくりも同時進行で進める必要があります。
マルチタッチアトリビューションの活用事例

実際にマルチタッチアトリビューションを導入している企業の活用シーンは多岐にわたります。ここでは代表的な事例を三つ取り上げ、その効果や学べるポイントを紹介します。
ECサイトでの広告最適化
複数の広告チャネルを使って新規顧客を獲得しようとするECサイトでは、広告施策の効果測定が極めて重要です。マルチタッチアトリビューションを採用することで、リスティング広告やディスプレイ広告、SNS広告などの組み合わせを効率化し、高いROAS(広告費用対効果)を達成しているケースがあります。
たとえば、SNS広告をクリックして商品ページを閲覧し、その後リマーケティング広告で購入が完了したケースを正しく評価できるため、最適な予算配分が可能になります。また、時間軸で顧客の動きを把握できるようになったことで、キャンペーンの打ち出しタイミングを的確に調整する企業も増えています。
BtoBの長期セールスサイクルへの応用
BtoB領域では、顧客獲得までに長い検討期間があることが多く、複数回のメール配信やオンラインセミナー、Web商談など多彩なタッチポイントが発生します。マルチタッチアトリビューションを利用すれば、どの接点がリードの温度感を高めているかを定量的に把握でき、営業活動の効率を上げられます。
具体的には、ABM(アカウントベースドマーケティング)と組み合わせて特定企業の行動履歴を解析し、その企業に対して最適な連絡手段や時期を判断するケースなどがあります。結果として成約率の向上や営業コストの削減が実現しやすくなるとされています。
オムニチャネル戦略での最適化
実店舗とオンラインストアの両方を展開している小売業では、顧客がスマホで商品情報を調べた後に店舗を訪れ、最後にECサイトで購入するといった行動パターンが多発します。マルチタッチアトリビューションを導入することで、オンラインとオフラインのデータを一元的に管理し、顧客の実際の行動経路を明確に把握できます。
その結果、店舗での接客方法や在庫配置に対しても、データに基づく改善施策を打ち出せるようになります。オムニチャネル時代には各チャネルを独立して評価するだけでは不十分であり、総合的な視点でのアトリビューションがより求められているといえます。